#0 熟したテーマは、向こうからやってくる
- moriameno
- Dec 10, 2022
- 4 min read
Updated: Jan 24, 2023
“熱したテーマは、向こうからやってくる”そう言ったのはフランスの文豪、バルザック。
そしてその言葉を引用した上で、「良い論文のテーマ」を考えつく過程を「醗酵」と呼んだのが日本の英文学者・外山滋比古である。
良質なテーマに必要なのは秀抜な「素材」と「酵素」であるらしい。つまり元となるアイディアとそこに変化を加えるヒントだ。日々の生活の中で出会うこの二つの要素を整理し、紹介するのがこのサイトの第一の目的となる。
加えて、醗酵の過程でいくら素材と酵素が良質でも、すぐに優れた醗酵食品(たとえばおいしいワイン)とならないのは、それをまず「寝かせる」必要があるからだという。
「頭の中の醸造所」でそっとしておく。すると忘れた頃に突然、動き出すらしい。その初動には高揚感があり、すでに一種に達成感もある。味わいのあるテーマの完成だ。いろいろな料理やワイン、オケージョンに合わせて楽しむことができるようになった。
様々な完成前の未熟な樽をそっと保管しておく場所としても、このサイトを利用してく。
自由気ままに追加される新しい樽の様子をぜひ楽しんでいただきたい。
数年後にはそれなりに見応えのあるワイナリーにでもなっているかもしれない。
醗酵させなければならない経緯
私は2023年4月から、論文テーマを考えなくてはならない立場に立たされる。二十四歳にして満を持して大学へ行くのである。
4年前にスコットランドの某大学の哲学科をたったの一年で休学して以来、学部すら卒業せずにのらりくらりフリーランス通訳者をやっている私だが、将来の夢は立派な学者になることだ。大学で働こうとする者が大学すら出ていないようでは話にならない。
紆余曲折の末やっと大学に戻ることを決め、日本のとある大学を受験した。幸いその大学では4年間で学士と修士が取れるとあって、時間のロスを多少は取り戻せると意気込んでいる。
4年間で2本の論文を書くのである。
楽しい苦悩は早いうちから始めておくべきだと思い立ち、こうして『醗酵日誌』を立ち上げた。
哲学科に通っていた頃、私には数多の悩みがあったが、その中でもエッセイのインスピレーションが湧いてくるのに時間がかかり過ぎるというのが一番困ったことだった。
良いアイディアはどのようにやってくるのか?
外山先生は「くりかえし、くりかえし、同じようなことをしていると、だいたい、どれくらいすれば醗酵が始まるか、見当もつき、心づもりをすることができるようになる。」とも書いている。良質な醗酵のための準備をした後は自然と時期が来るのを待ち、気長な作業を重ねていくと成熟の頃合いが勘でわかってくるらしい。
その「くりかえし」を習慣にできるうちにしておこう、というのが狙いだ。
このサイトでは私の学部から修士卒業までの4年間で起こる思考の移り変わりと成長を、醗酵の過程に例えて紹介していく。
結果として良い論文への軌跡をここに記せれば本懐だ。
どんな人にも届く「醗酵」を
日誌と言っても独壇場にならず、これから同じように論文を書き出そうとする人や、熱考を必要とするプロジェクトに取り組もうとしている人にとって有意義な読み物であることを心がけたいと思っている。
私の興味は哲学・言語・芸術であるため、日誌の題材そのものは読者の一部にしか有用性を持たないかもしれない。しかしながら、哲学という学問は特に、最古の学問らしく揺るぎないロジックの柱の元に立っている。その柱はどんな異端のテーマでも支えることができるものと信じている。畑違いの読者もぜひ何かを受け取っていってほしい。
また、論文など書く予定のない人にとっても面白い文章であるために、多少難解で学術的な内容を扱ってもそこに留まらない努力をしていくつもりだ。
知識を一般に応用できる「知恵」にまで変換する作業もまた、醗酵の一貫だということにする。
参考文献
『思考の整理学』外山滋比古/著
※ 醗酵も一歩間違えれば好ましくない菌が増殖するように、学問に「間違い」はつきものだ。正確さを欠く内容を発見した方、追記すべき内容をお持ちの方はぜひ、やさいしくご教示願いたい。
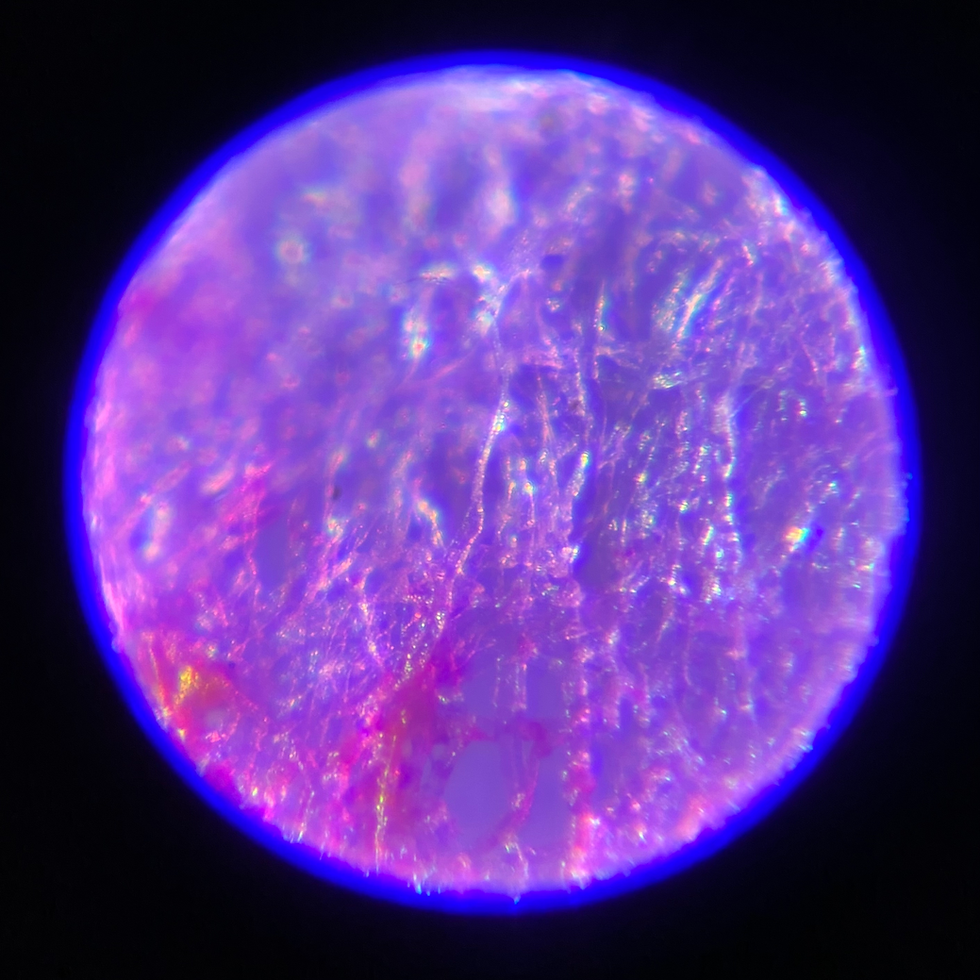
Comments